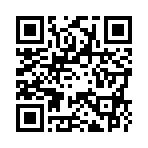2008年08月21日
急がば回れ
 「急がば回れ」という言葉は、
「急がば回れ」という言葉は、みなさんよく知ってますよね。
では、この言葉が生まれたのは
どこか知ってますか?
回ったのはどこを回ったのか知ってますか?
意外とそんなこと気にしてなかったでしょう!
実はこれは東海道の草津宿-大津宿間のことなんです。
この間の東海道を
地図で確認してもらうと分かりますが、
草津から西へ向かいますが、
途中から進路を南西に変え、
瀬田の唐橋で琵琶湖から出る瀬田川を渡ってます。
渡ると進路を北へ取り、
琵琶湖の湖岸近くまで行ってから西に曲がり、
大津宿へ至るというルートを取ってます。
つまり南へ大きく迂回しているのです。
そして、ここには草津宿の西の矢橋湊から
大津宿の打出浜まで琵琶湖を進む
矢橋の渡しがありました。
この舟で行く方が陸路より2里も近く、
早く着くのですが、
比叡下ろしの風が吹くことから、
舟が止まってしまったり、
悪いときには転覆したりしたことから、
遠くても確実な陸路の方が結局早いのです。
このことを室町時代の連歌師である宗長が、
「もののふの やばせの舟は 早くとも
急がばまわれ 瀬田の長橋」
と読んだことから、
急がば回れといわれるようになったということです。
現代の目で見るとたかだか8kmの遠回りですが、
歩くしかなかった時代の8kmは、
2時間の遠回りということになります。
こういう言葉って
中国の故事であることが多いですが、
静岡ともつながりのある
東海道の話とは意外ですね。
で、なぜ急がば回れかは、次の話に続きます。
Posted by hiroyuki at 19:13│Comments(0)
│街道歩き